
|
正弦波的でないことによる読み取りの困難さも一因である。特に周期が長い場合は、液状化させている砂地盤が有限であるため、乱れた波形となっている。
図−4〜8より以下のことが考えられる。
?基本的には、地盤層が厚いほど、また水深が浅いほど波高伝達率は小さくなっている。周期の影響については、当然ながらBs/Lが長いほど、すなわち周期が短いほど波高伝達率は小さくなるようである。ただし、第2章で述べたように、h/Lが小さいほど、すなわち周期が長いほど波高伝達率が小さくなる傾向もあり、特にT=1.0sと1.6sでは比較的差が少ない。
?最適な動水勾配は、波の波高や波長によって変わる可能性がある。すなわち、波の作用によって砂の流動化が促進される傾向があり、それによって最もエネルギーを消費する動水勾配が見かけ上変化することも考えられる。
?図−4の水深が50cmのケースは、図−5の水深が25cmのケースと比べると、水深だけでなく地盤厚さ、波長L、波高もほぼ2倍であり、地盤の長さBsのみが同じである。2つのケースの波高伝達率はほぼ同じような傾向を示しており、実験縮尺が2倍になった場合には、Bsが1/2になっても波高伝達率の変化はそれほど大きくないことがわかる。すなわち、同じ条件であれば模型が大きいほど波高伝達率が小さくなる可能性を示している。これは、前述の式(1)において、同じ地胆の場合、現地も模型も減衰係数Dが同じになるため、Dと距離xの積で表される波高減衰は、理論上は現地の方がより大きくなることを裏付けている。ただし、この点については縮尺を変えた模型実験によりさらに検討する必要がある。
4. 地盤による波の減衰に関するFEM計算
4-1. 計算の概要
波と地盤の相互作用および地盤の消波特性を検討するため、FEMを用いた数値計算も行い、模型実験結果との比較および模型と現地との違いについての検討を行った。計算はBiotによる二相弾性理論を用いており、地盤と水との境界では圧力だけでなく流れの連続性も満たし、地盤の動きと波の減衰を的確に表すことができる7)。ただし、計算を簡単にするため、断面二次元での周波数領域の線形計算としている。すなわち、速度ポテンシャルφと地疵および間隙水の変位u、πは以下のように表される。
φ=Re[Φe−jωt] (6)
u=Re[Ue−jωt] (7)
w=Re[We−jωt] (8)
ここに、u、wは水平成分および鉛直成分からなるベクトルであり、φは複素数、U, Wは複素数からなるベクトルである。
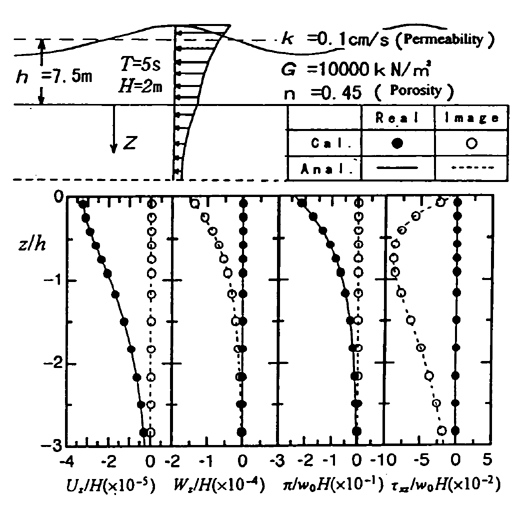
Fig-9 Pore Pressure and Sand Displacement Generated by Waves.
4−2.砂地盤内と波の相互作用
計算の妥当性を確認するため、まず平坦な砂地盤上を進行波が通過する場合の計算を行った。図―9は、透水係数k=0.1cm/s、せん断弾性係数G=10000kN/m2、空隙率n=0.45で、無限深さを有する地盤に対して、水深h=7.5mで、周期T=5s(波長L=34.7m)、波高H=2mの波が作用したときの計算結果である。図には、波の峰が到達した時点における間隙水圧π、土骨格の鉛直変位Uz、間隙水の変位Wz、そしてせん断応力τxzについてその実部と虚部を示している。
それぞれの結果について実部に着目すると、この例のように硬い砂では波と砂地理表面の動きは180度ずれており、その振幅も0.06mmと小さいことがわかる。また、間瞭水の地盤表面での変位はその振幅が0.3mmと地盤表面の動きより大きく、位相は波より90度だけ進んでいる。間隙水圧については、表面では当然波圧と同じであるが、1/4波長の深さ(図中においてz/h=−1.15)程度で地盤表面の1/4とかなり小さくなっており、位相は波と同位相で、ずれは生じていない。なお、砂地盤内の間隙水圧は引っ張りを正としているので、図では負の値となっている。
こうした傾向は、すでに多くの研究によって確かめられたとおりである。図中の実線および波線で示した山本2)の計算値ともよく一致しており、この計算法の有効性が確かめられた。
図−9に示した計算を用いて、地盤の動きによる波の変化も計算できる。山本ら5)は、多層地盤についてこうした計算を行っており、特に地盤による波の減衰を検討して、せん断弾性係数が小さい軟らかい地盤では、波長の変化と波高の減衰が発生することを示している。
図−10は、模型実験と同じ条件、すなわち砂地盤の長
前ページ 目次へ 次ページ
|

|